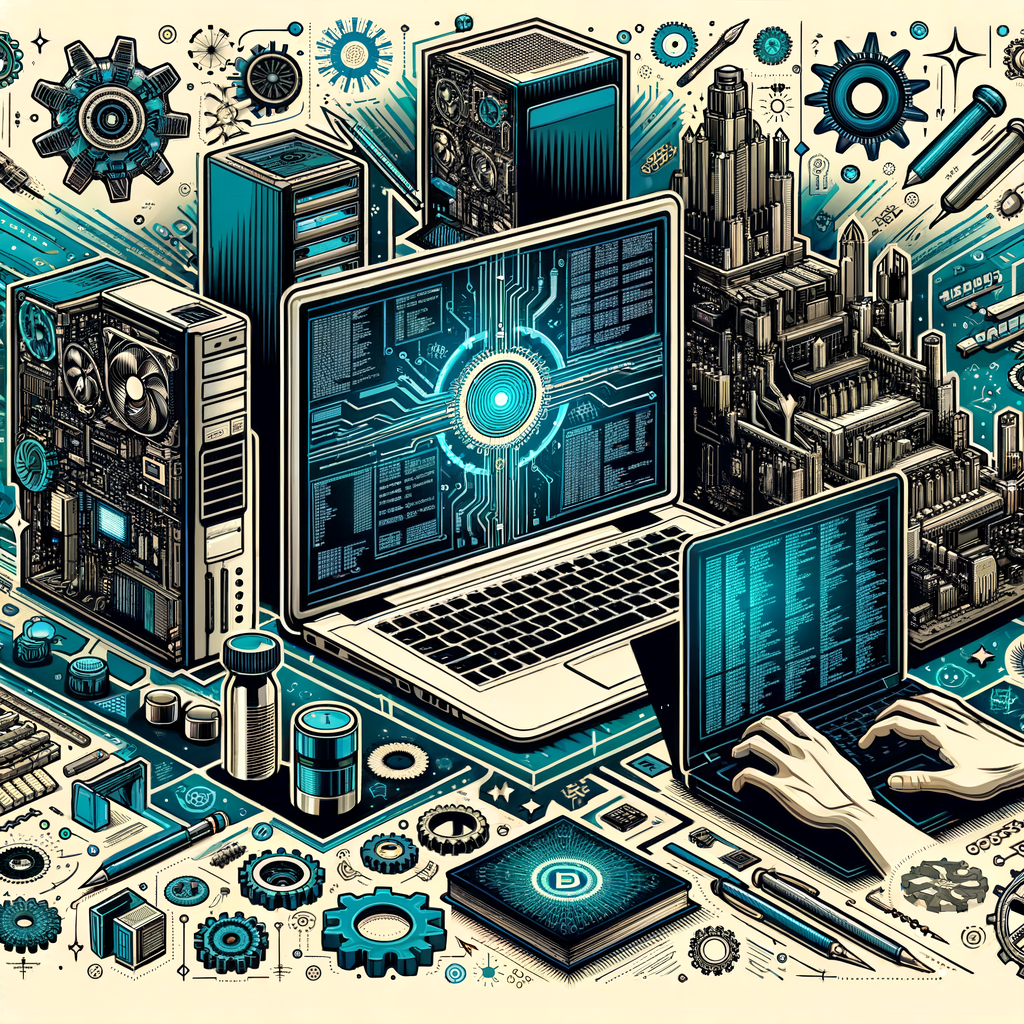パソコンを日常的に使っているあなたでも、「BIOS」という言葉を耳にすると、少し身構えてしまうことはありませんか?
「なんだか難しそう」「触ると壊れそう」――そんなイメージをお持ちの方は、決して少なくありません。
しかし、BIOS(バイオス)は、パソコンの“心臓部”とも言える重要な設定画面であり、ちょっとした知識があるだけで、起動トラブルの解決やシステムのカスタマイズがぐっと身近になります。
この記事では、初心者でも安心してBIOSを起動し、必要な設定ができるようになることを目指して、メーカー別の起動キー一覧から、設定変更の方法、トラブル時の対処法までを丁寧に解説します。
「パソコンの調子がおかしい……」「USBから起動したいのにできない……」という時、BIOSを理解しているかどうかが大きな差になることも。
パソコンに詳しくない方でも大丈夫。この記事を読めば、BIOSに関する不安は解消され、トラブルに強い“脱・初心者”を目指せます!
さあ、まずは「BIOSとはなんなのか?」を一緒に見ていきましょう。
BIOS起動キーの表
| メーカー | 主なBIOS起動キー | その他のキー / 補足 |
|---|---|---|
| Dell | F2 | F12でブートメニュー(USB/DVD起動) |
| HP | Esc → F10 | Escでスタートアップメニュー表示後、F10でBIOSへ |
| Lenovo | F2 または F1 | ノートPCは「Novoボタン」からもBIOS/ブートメニューにアクセス可能 |
| ASUS | F2 または Delete | 自作PCやデスクトップはDelete、ノートPCはF2が主流 |
| Acer | F2 | 機種によってはDeleteやF12も使用可能 |
| Toshiba | F2 | 古いモデルではEsc → F1でBIOS起動 |
| NEC | F2 | 機種によってはF11やF12を使用する場合あり |
| 富士通 | F2 または F12 | 一部モデルで「Assistボタン」からBIOSへアクセス可能 |
| ASUS(マザーボード) | Delete または F2 | 自作PC向けマザーボードはDeleteが基本 |
| MSI | Delete | ゲーミングシリーズも含めDeleteが標準 |
| Gigabyte | Delete または F2 | Deleteが基本だがF2対応モデルもあり |
| ASRock | Delete または F2 | モデルにより異なるがDeleteが主流 |
| BIOSTAR | Delete | シンプルにDeleteキーでBIOS起動 |
BIOSとは何か?その基本知識
パソコンを起動したとき、Windowsが表示されるまでの間にほんの一瞬だけ活躍する、まさに「縁の下の力持ち」的存在――それがBIOSです。BIOS(バイオス)とは「Basic Input/Output System」の略で、パソコンのハードウェアとソフトウェアの橋渡しをする基本的なシステムです。
なぜ理解しておくべきか
BIOSはふだん意識せずに使っていても問題ありませんが、トラブル時やパソコンの初期設定、OSの再インストールなどの場面では、その知識がとても重要になります。 特に自作PCや古いPCを使っている方にとっては、必ず押さえておきたい基本事項です。
BIOSはパソコンとユーザーをつなぐ「入口」です。ほんの少しでも理解しておくことで、トラブル対策やカスタマイズにも役立つでしょう。
BIOS起動の一般的な注意点
パソコンの設定やトラブルシューティングで欠かせないのがBIOSの起動です。しかし、「キーを押しても反応しない」「BIOS画面が出てこない」といった困りごともよくあります。BIOSをスムーズに起動するには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
起動タイミングに注意
BIOSを呼び出す際は、パソコンの電源を入れてからすぐに特定のキー(F2、Delなど)を押す必要があります。タイミングが非常に重要で、遅いとOSが起動してしまい、早すぎると認識されないことも。そのため、電源ボタンを押したらすぐに連打するのがコツです。
キーボードの種類にも注意
一部の機種では、ワイヤレスキーボードやBluetoothキーボードが電源投入直後に認識されないことがあります。BIOS起動の際は、有線USB接続のキーボードを使用するのが安心です。また、ノートパソコンでは「Fn」キーとの組み合わせ(例:Fn + F2)が必要な場合もあるため、取扱説明書の確認もおすすめです。
高速起動設定が邪魔になることも
Windows 8以降のパソコンでは、「高速スタートアップ」や「Fast Boot」機能によって、BIOSを起動する時間が極端に短くなってしまうことがあります。この場合、Windows上から再起動し、「Shift」キーを押しながら「再起動」を選択し、トラブルシューティング→UEFIファームウェア設定からBIOSに入る方法が有効です。
画面表示をよく確認する
起動時の画面に、「Press F2 to enter Setup」などと表示されることがあります。この表示は数秒しか出ないため、見逃さないことが大切です。一瞬のチャンスを逃さないように、起動直後から注視しましょう。
これらのポイントを意識するだけで、BIOS起動時のストレスを軽減し、スムーズな設定変更が可能になります。慌てず、確実に起動させる知識を身につけておきましょう。
メーカー別BIOS起動キー一覧
パソコンのBIOS(またはUEFI)を起動するためには、電源投入直後の一瞬のタイミングで特定のキーを押す必要があります。この起動キーは、メーカーやモデルによって異なるため、事前に把握しておくことがとても重要です。ここでは、主要なパソコンメーカー別に、よく使われるBIOS起動キーをご紹介します。
Dell(デル)
Dellの多くのモデルでは、[F2]キーを押すことでBIOS設定に入ることができます。また、[F12]キーを使えばブートメニューにアクセスでき、USBやDVDからの起動にも素早く対応できます。
HP(エイチピー)
HPパソコンでは、[Esc]キーでスタートアップメニューを呼び出し、その後[F10]キーでBIOSに入る形式が一般的です。ロゴ画面が出たらすぐにEscを連打するのがコツ。
Lenovo(レノボ)
Lenovoはモデルによって起動方法が少し異なりますが、多くは[F2]あるいは[F1]キーが使われます。ノートパソコンの場合、「Novoボタン」と呼ばれる専用の小さな物理ボタンが側面にあり、ここからも簡単にBIOSにアクセスできます。
ASUS(エイスース)
ASUSのパソコンは、[F2]キーまたは[Delete]キーが基本です。とくに自作PC向けのマザーボードではDeleteキーをよく使用します。
Acer(エイサー)
Acerでは、[F2]キーが最も一般的。ただし機種によっては[Delete]キーや[F12]も対応しているので、複数のキーを試すとよいでしょう。
Toshiba(東芝)
東芝製ノートPCでは、[F2]キーでBIOS起動が可能です。古いモデルでは[Esc]キーを使用するものもあるため、型番に応じた注意が必要です。
NEC・富士通など国産メーカー
日本メーカーは機種によるバリエーションが多く[F2]、[F12]、[F11]など複数の起動キーが存在します。正確な操作方法はメーカーのサポートページやマニュアルを参照するのが確実です。
BIOSへの正しいアクセス方法を知ることは、トラブル時の迅速な対応や設定変更において非常に重要です。お使いのPCのメーカーと機種に合ったキーをあらかじめ把握しておきましょう。
DellパソコンのBIOS起動キー:機種ごとの違いに注意
基本的な起動キー
DellのパソコンでBIOSを起動する際、もっとも一般的に使用されるキーは[F2]または[Delete]キーです。パソコンの電源を入れた直後、メーカーのロゴが表示されているタイミングでこれらのキーを押すことで、BIOS設定画面にアクセスできます。
このタイミングは非常に短いため、確実に入るには電源を入れてから素早く[F2]キーを連打するのがコツです。うまくいかない場合は、電源を切って再チャレンジしてみましょう。
ブートメニューへのアクセス方法
BIOS設定ではなく、USBやDVDなどのブートデバイスを一時的に変更したい場合には、[F12]キーが活躍します。これにより、「Boot Menu(ブートメニュー)」が表示され、接続されたデバイスから直接起動することが可能です。
特にWindowsの再インストールや、USB起動が必要なツールを使う際に便利な機能です。
モデルによる違い
Dellのノートパソコンやデスクトップには多くのモデルが存在し、一部の機種では起動キーが異なる場合があります。たとえば、XPSシリーズやLatitudeシリーズでは高速起動設定が有効になっているため、キー入力が間に合わないこともあります。その場合、Windows上から[Shift]キーを押しながらの再起動で「UEFI設定」へ進むという方法もあります。
確実にBIOSに入るためのポイント
BIOSにうまく入れない場合は、まず外付けキーボードではなく、PC直付けの有線キーボードを使用するのが安全です。また、ノートPCが高速スタートアップを有効にしているとキーが無効化されることがあるため、Windows側の設定を一時的に変更するのも手です。
DellパソコンでのBIOSアクセスは、機種ごとの特性を把握することが成功の鍵。一度操作に慣れてしまえば、設定変更やトラブル対応にとても便利になるので、焦らず試してみてください。
HP
HPパソコンでBIOSに入る基本操作
HPのノートパソコンやデスクトップでBIOSへアクセスするには、起動時に[Esc]キーを押すのが基本の操作です。電源を入れてすぐに[Esc]キーを連打すると、スタートアップメニューが表示されます。このメニュー画面には、システム情報、システム診断、起動デバイスの選択、BIOS設定などへのショートカットキーが並んでいます。この中から[F10]キーを押すことで BIOS(UEFI設定)へ入ることができます。
この操作は、Windowsが起動してしまう前に行う必要があるため、一瞬のタイミングが重要です。起動ロゴが表示された直後、あるいはロゴが出る前から[Esc]キーを何度も押しておくことで、確実にスタートアップメニューを呼び出すことができます。
うまくいかないときの対処法
もし[Esc]キーを押してもスタートアップメニューが表示されない場合は、次の点を見直してみましょう。まず、USBやBluetoothのキーボードでは反応しないことがあるため、有線キーボードを使うのがベストです。また、近年のHP製品では「高速起動」機能がオンになっていて、BIOS画面に入る猶予が極端に短くなっている場合もあります。この場合は、Windows上から「Shiftキーを押しながら再起動」し、「UEFIファームウェアの設定」からBIOSにアクセスする方法もあります。
機種による微妙な違いに注意
HPではモデルによりキー操作が若干異なることもあります。たとえば、ビジネスモデルや企業向け機では専用のメニュー構成やセキュリティが追加されている場合も。正確な手順やキー操作は、お使いの機種のユーザーマニュアルを参照するのが確実です。
HP独自の手順に慣れていないと戸惑うかもしれませんが、一度手順を覚えてしまえば操作は非常にシンプルです。トラブル時や設定を変更したいときのために、BIOSの入り方はしっかりマスターしておきましょう。
Lenovo
Lenovoパソコンを使用していると、「いざという時にBIOSを開きたいのに方法が分からない」といったケースは意外と多いものです。BIOSはトラブルシューティングやOS再インストール時に重要な役割を果たしますので、操作方法をしっかりと理解しておくことが大切です。この記事では、Lenovo製パソコンのBIOS起動方法を分かりやすく解説します。
基本的な起動キー
LenovoのBIOSにアクセスするためには、再起動時または電源投入時に[Fn]キーを押しながら[F2]キーを押すのが一般的です。ThinkPadシリーズなどのビジネスモデルでは、[F1]キーのみで起動するタイプもあります。モデルによって挙動が異なるため、起動直後のロゴ画面に表示されるガイド文(”Press F1 to enter Setup”など)をよく確認しましょう。
Novoボタンとは?
Lenovoの一部のノートパソコンには「Novoボタン」という専用のBIOS起動用ボタンが搭載されています。このボタンは本体側面やキーボードの近くに小さな穴状で配置され、ペン先やSIMイジェクターピンなどで押すことで、特殊なメニュー(Novo Menu)を表示させることができます。
Novo Menuからは、「BIOS Setup」「Boot Menu」など複数の選択肢が表示され、通常のキー操作ができない状態でもBIOSへスムーズにアクセスすることが可能です。
注意点と補足
Lenovoの一部モデルは高速起動が有効になっていると、BIOSキー入力を受け付けないことがあります。その場合は、Windows上から「Shiftキーを押しながら再起動」 → 「UEFIファームウェアの設定」からBIOSにアクセスすることもできます。
また、Fnキーの挙動がBIOS設定内で逆転(Fnロック)されていることがあり、その際には[F2]キー単体での操作も試してみるとよいでしょう。
Lenovoユーザーならではの便利な機能と注意点を理解しておくことで、トラブル時も落ち着いて対処できるようになります。
ASUS
ASUS製PCのBIOSにアクセスする方法
ASUSのパソコンやマザーボードでBIOSに入るには、基本的には[F2]キーまたは[Delete]キーを起動時に押すのが一般的です。電源を入れてすぐ、メーカーのロゴが表示された瞬間にこれらのキーを押すことで、BIOS(またはUEFI)設定画面に入ることができます。
デスクトップPCや自作PCの場合は、[Delete]キーが使われることが多いのが特徴です。一方でノートパソコンでは[F2]キーが主に使われます。誤ってタイミングを逃すとWindowsが起動してしまうため、電源を入れたらすぐに該当キーを連打すると確実です。
BIOSに入れないときの注意点
もし[F2]や[Delete]キーを押してもBIOSに入れない場合、キーボードの反応が遅れているか、Fast Boot(高速起動)が有効になっている可能性があります。この場合は、Windows上から「Shiftキーを押しながら再起動」を行い、起動メニューから「UEFIファームウェア設定」を選ぶ方法も試してみましょう。
また、USB接続のキーボードが認識されていないケースもあるため、できるだけ有線のUSBキーボードを使用するのもポイントです。
モデル別の違いもチェック
ASUSの全モデルが同じ操作とは限りません。ゲーミングモデルやROGシリーズ、商用モデルなどでは仕様が異なる場合もあります。お使いの製品がどのモデルかを確認し、念のためメーカーの公式サポートページやマニュアルをチェックしておくと安心です。
BIOSはシステムの心臓部ともいえる大切な設定エリアです。誤って設定を変更してしまわないよう、操作には十分ご注意ください。何かあった場合に備え、設定を変更する前には現状をメモしておくと安全です。
Acer
AcerパソコンのBIOS起動に使うキーは?
Acer(エイサー)のパソコンでBIOSを起動するには、通常は[F2]キーを起動ロゴが表示されるタイミングで押すのが一般的です。ですが、モデルや発売時期によっては[F12]や[Delete]キーが割り当てられている場合もあるため、状況に応じて複数のキーを試してみるとよいでしょう。
特にデスクトップモデルでは[Delete]キーが有効なことが多く、逆にノートパソコンは[F2]キーが主流。どのキーを使うか迷った場合は、起動時に画面下部に「Press F2 to enter Setup」といったメッセージが表示されるか確認してみてください。表示される時間は非常に短いため、電源を入れてすぐに連打するのがコツです。
うまくBIOSに入れない場合のヒント
「何度試してもBIOSに入れない…」という経験がある方も多いのではないでしょうか。そんなときは、次の対処方法を参考にしてみてください。
– USBキーボードやBluetoothキーボードが認識されず、キー入力が無効になるケースがあります。その場合は、有線キーボードを使って試すのが効果的です。
– Windowsが高速起動モードになっていると、キー入力の受付が極端に短くなりBIOSに入れないことも。Windowsから「Shiftキーを押しながら再起動」→「UEFIファームウェア設定」を選ぶ方法でBIOSに入ることも可能です。
Acer公式サイトで最新情報をチェック
Acerは世界で広く支持されるブランドで、機種のバリエーションが非常に多いため、モデルごとのBIOS起動キーが異なることがあります。もし手元のPCでどのキーが該当するか不明な場合は、Acerの公式サイトやサポートページでマニュアルをダウンロードして確認するのが確実です。
正しいキーを押すタイミングさえつかめば、BIOSには難なくアクセスできます。焦らず、一呼吸おいて電源投入時からキーを押してみましょう。
ToshibaのパソコンでBIOSを起動する方法
Toshiba(東芝)のノートパソコンやデスクトップには、多くのモデルが存在し、それぞれでBIOSの起動方法に少し違いがあります。BIOS設定にアクセスすることで、起動順序の変更やハードウェアの確認、セキュリティ設定など幅広い管理が可能になります。この記事では、Toshiba製PCにおける代表的なBIOS起動方法をわかりやすく解説します。
基本は[F2]キーを押す
Toshibaの多くのモデルでは、電源を入れた直後に[F2]キーを連打することでBIOS画面へアクセスできます。起動ロゴが表示された瞬間に押すのがポイントで、タイミングが早すぎても遅すぎても認識されないことがあります。特に最近のモデルでは高速起動機能が働いていることがあるため、数回押すというよりも「連打」する感覚で操作すると成功率が高くなります。
古いモデルでは[Esc]キーが必要なことも
古いToshibaの機種では[F2]ではなく、[Esc]キーを使用することでBIOSへ入るタイプも存在します。この場合、電源投入後すぐに[Esc]キーを押すと、一時的なメッセージや指示が表示され、そのまま[F1]キーを押してBIOS画面が表示される流れになることが一般的です。自分が使っている機種がどの方式なのか不明な場合は、電源投入後にどちらのキーでも反応がないか試してみましょう。
困ったときはマニュアルやメーカーサポートを活用
BIOSに入れない、起動キーがわからないといった場合は、Toshiba製品の公式マニュアルやサポートサイトを確認するのが確実です。型番によっては全く異なる手順になっているケースもあるため、特に法人向けモデルや旧型モデルを使っている場合は、公式情報が大いに役立ちます。
BIOSの操作はシステムに大きな影響を与える可能性がありますが、正しい手順を知っておけば安心して扱うことができます。焦らず、落ち着いて操作を行うことが成功のカギです。
NEC・富士通など日本メーカー
メーカーごとに操作方法が異なるのが特徴
日本の主要PCメーカーであるNECや富士通のパソコンでは、BIOSを起動するためのキーが機種によって大きく異なるという特徴があります。同じメーカーでも、モデルや発売時期によってキー設定が異なることが多いため、起動キーを調べる際には細心の注意が必要です。
一般的にはNECでは[F2]キー、富士通では[F2]または[F12]キーが主流です。ですが、一部機種では[F11]キーや「Assistボタン」を使用する場合もあります。最新のノートパソコンやビジネス向けモデルほど、メーカー独自の仕様が加わっているケースが多いため注意が必要です。
まずはマニュアルやメーカーサポートを確認
このようにモデルによって起動キーがまちまちであるため、確実な方法は「取扱説明書」や「メーカー公式サポートページ」で確認することです。モデル番号を検索すれば、該当機種のBIOS起動方法が明記されていることがほとんどです。特に法人向けモデルやカスタム仕様のモデルでは、BIOSへのアクセス法が独自設定になっていることもあるため、自己判断は禁物です。
マニュアルが手元にない場合の工夫
もしマニュアルや説明書が手元にない場合、起動時に表示されるメッセージをよく見ることもヒントになります。多くのモデルでは、起動直後に「Press F2 to enter Setup」などと表示されることがあります。この表示はほんの数秒間なので、見逃さないよう注意しましょう。また、起動直後に写真を撮って確認したり、ビデオで録画して後から確認するという工夫も役に立ちます。
正しいBIOS起動キーを把握することで、トラブル時にも迅速に対応できるようになります。モデルに合わせた正しい操作を行い、安全に設定を進めていきましょう。
BIOS起動時の画面の見方
パソコンの電源を入れてすぐにBIOSへアクセスしたとき、画面にずらりと並ぶ英語や項目に戸惑った経験はありませんか?BIOSの画面は直感的ではないため、慣れていない方には難しそうに見えるかもしれません。しかし、一度基本の見方を押さえれば、必要な設定変更もスムーズに行えるようになります。
全体の構成を把握する
BIOSの画面はメーカーやモデルによって少しずつ異なりますが、基本的には「Main(情報)」「Advanced(詳細設定)」「Boot(起動順)」「Security(セキュリティ)」「Exit(終了)」などの項目に分かれています。画面上部や左側にタブ状で表示されているので、キーボードの矢印キーで移動しながら操作します。
システム情報を確認
「Main」タブでは、現在搭載されているCPUやメモリの容量、日付や時間など基本的なシステム情報をチェックできます。起動時に不具合があった場合、まずここで認識されているハードウェアを確認するのが重要です。
起動順位の変更
OSの再インストール時や、USBからブートしたいときには「Boot」タブを確認します。ここでの設定で、どのデバイスを優先して起動するかを変更できます。USBメモリにWindowsのインストールメディアを入れている場合などは、最上位にUSBを設定する必要があります。
設定値の保存と終了方法
設定を変更したら「Exit」タブに移動して保存が必要です。一般的には「Save and Exit」やF10キーを押すことで、変更を保存して再起動します。変更を取り消して終了したいときには「Discard Changes and Exit」を選びましょう。
少し取っつきにくく感じるBIOS画面も、構成と基本操作を押さえておけば無駄なく活用できます。何を変更したかを把握し、必要に応じて元に戻せるように注意して操作しましょう。
BIOS起動ができない時の対処法
パソコンのトラブルシューティングや設定変更のためにBIOSを起動しようとしても、「何度キーを押しても入れない……」と困った経験はありませんか?最近のPCは高速起動機能などの影響で、想像以上にBIOS画面へのアクセスが難しくなっているケースがあります。ここでは、BIOSが起動できない場合の原因と対処法についてご紹介します。
キーのタイミングと連打が大切
まず確認すべきは、正しいタイミングで正しいキーを押しているかです。起動直後のメーカーのロゴが表示される瞬間に、指定されたキー(多くの場合F2やDelete)を素早く連打するように押すのがコツです。キーを1回だけ軽く押しても反応しない場合があるので、何度か試してみましょう。
USBキーボードが認識されていない?
一部のPCでは、起動時にUSBやBluetoothキーボードが認識されないことがあります。その場合は、有線のPS/2キーボードやUSBポートに直接接続されたキーボードを使用して試すのが効果的です。特に自作PCユーザーや古い機種をお使いの方は注意が必要です。
WindowsからBIOSに入る方法
キー操作でBIOSに入れない場合でも、Windows 10や11には「UEFIファームウェア設定」からBIOSに入る機能があります。方法は、
1. [設定] → [更新とセキュリティ] → [回復]
2. [今すぐ再起動] をクリック
3. 「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「UEFIファームウェア設定」
この手順でも安全にBIOSへアクセス可能です。
その他の最終手段
どうしてもBIOSが開けない場合は、CMOSクリアを行うことで設定をリセットできます。ただしこれは最終手段であり、取り扱いには十分な注意が必要です。やり方はマザーボードのマニュアルを確認するか、メーカーのサポートに問い合わせましょう。
「BIOSに入れない」状態は、原因さえわかれば対処可能です。ひとつずつ試して、焦らず解決していきましょう。
ノートパソコン特有の注意点
ノートパソコンでBIOSを起動しようとした際、「デスクトップと同じ方法ではうまくいかない」と感じたことはありませんか?実は、ノートパソコンには BIOSを開く際にいくつか特有の注意点 があります。ここでは、安心してBIOSにアクセスするために知っておきたいポイントをご紹介します。
Fnキーとの組み合わせに注意
最近のノートパソコンでは、ファンクションキー(F1~F12)が音量調節や画面の明るさ調整などのショートカットに割り当てられていることが多く、そのまま押しても期待する動作をしないことがあります。BIOSへ入るための「F2」キーや「Delete」キーが反応しない場合は、「Fnキー」との同時押しを試してみましょう。
電源ボタンや専用ボタンが用意されている場合も
Lenovoの「Novoボタン」や、富士通、Sonyなどの「Assistボタン」など、一部のメーカーではBIOS専用の物理ボタンを搭載しています。これらのボタンは電源オフの状態から押すと、BIOS設定画面やブートメニューに直接アクセスできる便利な機能です。該当機種をお使いの方は、マニュアルで位置を確認しておくと安心です。
バッテリー残量にも注意が必要
BIOSの設定変更中に電源が切れることは非常にリスクが高いです。バッテリーが極端に少ない状態だとBIOS画面に入れなかったり、自動的にシャットダウンしたりする可能性があります。BIOSにアクセスする際は、必ずACアダプターを接続しておきましょう。
タッチパッドやUSBポートの反応に違いがあることも
BIOS画面では多くの場合、タッチパッドや一部の外部デバイスが使用できないことがあります。そのため、外付けマウスや有線キーボードの用意があるとより確実に操作できます。
ノートパソコンでは多くの便利機能がある反面、BIOSへのアクセス方法も千差万別です。使用しているモデルの仕様をしっかり確認したうえで、安全にBIOS操作を行いましょう。
UEFIとレガシーBIOSの切り替え方
パソコンを新しく構成する際や、古いOSをインストールしたいときに関わってくるのが「UEFI」と「レガシーBIOS」のモード切り替えです。この設定を誤ると、OSがインストールできなかったり、起動トラブルの原因になるため、非常に重要なポイントです。
UEFIとレガシーBIOSって何が違う?
まず、UEFI(ユーイーエフアイ)とレガシーBIOSの違いを簡単に説明しましょう。UEFIは最新のシステム起動方式で、高速起動やセキュアブートなどの安全性を備えているのが特徴です。一方、レガシーBIOSは旧来の仕組みで、古いOSや一部のハードウェアとの相性を考慮する場合に用いられます。
切り替える理由と注意点
例えば、Windows 11をインストールするならUEFIモードが必須です。ただし、古いOSや特定のツールを使いたい場合は、レガシーBIOSに切り替える必要が出てきます。ただし、モードを切り替えると既存のOSが起動しなくなる場合があるので、大切なデータがある場合は事前にバックアップを取りましょう。
切り替え手順の基本
BIOS(またはUEFI設定)に入り、「Boot」タブや「Advanced」などの項目にある「Boot Mode」または「UEFI/Legacy Boot」といった設定を探します。ここで、「UEFI」または「Legacy(CSM)」を選択して保存すれば切り替え完了です。一部のマザーボードでは「CSM(Compatibility Support Module)」という項目で設定することもあります。
OSインストール時は要注意
USBインストールメディアがUEFI形式で作成されているかどうかもポイントになります。たとえば、UEFIモードで起動するときは「UEFI: USBデバイス」のように表示されるものを選択しましょう。レガシー形式ではただ「USBデバイス」とだけ表示されることが多いです。
モード設定はパソコンの動作に大きく関わるため、不安な場合はメーカー公式のマニュアルやサポートを事前に確認することが大切です。
自作PCやマザーボードメーカー別のBIOS起動キー
自作PCの場合、BIOSにアクセスする際のキーは、使用しているマザーボードのメーカーによって異なります。正しいBIOS起動キーを押さえておくことで、スムーズにシステム設定へアクセスできるため、少しでも違和感を感じたら確認しておきましょう。
マザーボード各社の起動キー早見表
以下は主要マザーボードメーカー別のBIOS起動キーです。多くの場合は、起動直後のロゴ画面に「Press ○○ to enter Setup」などと表示されるため、そこに注目してみてください。
– ASUS(エイスース):Delete または F2
自作PC向けで人気のASUS製マザーボードは、Deleteキーが主流です。ごく一部のモデルではF2キーが対応していることもあります。
– MSI:Delete
MSI製マザーボードも、一般的にはDeleteキーでBIOSへ。特に「Gaming」シリーズなどはロゴ画面にしっかりとキー案内が出ることが多いです。
– Gigabyte(ギガバイト):DeleteまたはF2
モデルによりますが、多くのGigabyte製ボードではDeleteキーが基本。ただし、F2でもアクセス可能なモデルもあるため、両方試す価値ありです。
– ASRock(アスロック):Delete または F2
コストパフォーマンスに優れたASRock製品でも、Deleteが一般的。F2が有効な場合もあるため、複数キーで試すのがおすすめです。
– BIOSTAR(バイオスター):Delete
バイオスター製マザーボードは比較的シンプルで、DeleteキーでのBIOS起動が定番です。
起動タイミングと注意点
BIOSへ入るには、電源を入れてすぐに該当キーを連打するのがコツです。キー入力が遅れるとOSが起動してしまうため、電源ボタンを押した瞬間から数回連打しておくと安心です。また、キーボードがUSB接続かつ初期認識されない場合は、PS/2接続のキーボードを併用すると確実になります。
マザーボードによってはセキュアブートや高速起動が有効になっているため、WindowsからBIOSへ入る方法も覚えておきましょう。設定変更やドライバ更新を行う場合に役立ちます。
自作PCならではの柔軟性を活かすためにも、各メーカー固有の操作を把握しておきたいですね!
BIOS設定変更後の保存と終了方法
BIOSの設定を変更した後、その内容を正しく保存しないと、せっかくの作業が無意味になってしまいます。設定を反映させるためには、保存と終了の操作が不可欠です。ここでは、各メーカー共通の基本的な手順と、注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。
保存して終了する基本操作
BIOS画面から設定を変更した後、正しく保存して終了するには、通常「F10」キーを使用します。[F10]キーを押すと「Save and Exit」もしくは「Exit Saving Changes」などの確認メッセージが表示され、「Yes」を選択すれば変更内容が反映されてPCが再起動します。これにより、新しい設定が有効になります。
一部の種類では、画面下部に「Save Changes and Reset(変更を保存して再起動)」といった項目があり、マウス操作で選択することも可能です。最近のUEFI BIOSでは視覚的にも分かりやすいインターフェースが採用されており、タブやボタンをクリックするだけでこの操作ができます。
設定を保存せずに終了するには?
もし設定を試してみたものの、保存する必要がないと感じた場合には「Exit Without Saving」や「Discard Changes and Exit」といったオプションを選択することで、設定を反映せずにそのまま終了できます。これも[F10]以外のキー(例:[Esc]や指定タブ)から選べることが多いので、迷うことはありません。
保存時の確認画面に注意
ほとんどのBIOSでは、終了前に「本当に保存して終了しますか?」という確認画面が表示されます。ここで「Yes」を選ばないと保存されずにキャンセルされてしまいます。変更を失わないためにも、この確認画面では確実に「Yes」を選ぶようにしましょう。
BIOSの設定変更後は、保存と終了の操作までがセットです。うっかり保存を忘れると、何度もやり直す羽目になりかねません。一度の作業で確実に設定を反映させるためにも、保存操作の確認は丁寧に行いましょう。
間違った設定変更を元に戻す方法
BIOSをいじっていると、「あっ、設定間違えたかも…」なんて不安になることもあるでしょう。でも安心してください。BIOSは間違った設定を元に戻せる機能がちゃんと備わっています。ここでは、BIOS設定を安全に初期状態に戻すための方法をご紹介します。
「Load Default Settings」で初期化
ほとんどのBIOSには「Load Setup Defaults」または「Load Optimized Defaults」というオプションがあります。これは工場出荷時の安定かつ推奨される設定に戻す機能です。
操作は簡単で、BIOSメニュー内でこの項目を選び、「Yes」などで確定すればOK。急な変更でパソコンが不安定になったときの定番リセット方法です。
CMOSクリアで完全リセット
上記で解決しない場合や、BIOS自体に入れなくなってしまったときは「CMOSクリア」という方法があります。これはマザーボード上の設定情報を保持するCMOSメモリを物理的にリセットする方法です。
多くの場合は、PC電源をオフにし、マザーボードの「CMOSクリアジャンパ」を指定の位置に動かすか、CMOS電池(丸いコイン形)を一時的に取り外すことでリセットが可能です。ただし、機種や構造によって異なるため、マザーボードのマニュアルを確認しましょう。
安全に元へ戻すために
焦って手当たり次第に設定を変えるのはNGです。設定を変える前には、写真を撮ったりメモを取ったりして、元の状態を記録しておくのが賢いやり方です。また、異変を感じたら早めに「Load Defaults」で戻すのがおすすめです。
BIOSは便利ですが慎重に扱うべき領域です。「大丈夫、元に戻せる」という安心感を持ちながら冷静に操作していきましょう。
まとめと安全な取り扱いの注意点
BIOSはパソコンの最も重要な設定が集約されている場所であり、使いこなせれば非常に便利な半面、誤った操作をすると思わぬトラブルを招くこともあります。操作ミスや知識不足によって、システムが起動しなくなるリスクもあるため、慎重な取り扱いが不可欠です。ここでは、安全にBIOSを扱うために心がけたいポイントをまとめました。
設定変更は必要最低限にとどめる
BIOSには多くの機能や設定項目がありますが、初心者がすべての項目を触る必要はありません。起動順位の変更や、仮想化機能の有効化など、目的がはっきりしている項目だけを変更するよう心がけましょう。不要な設定変更は、思いがけないエラーや動作不良の原因になります。
変更後は保存方法に注意する
設定を変更したあとは、「Save and Exit」や[F10]キーで正しく保存して終了する必要があります。設定を保存せずに終了すると、せっかくの変更が無効になるだけでなく、再度やり直しになる場合もあります。また、誤って保存してしまった場合は、BIOS画面から「デフォルトに戻す」機能を活用しましょう。
マニュアルやサポートを活用する
BIOSの画面や操作方法はメーカーやモデルによって異なります。操作に不安がある場合は、公式マニュアルやサポートサイトを確認することで、安全かつ確実に対応が可能です。困ったときは無理せず専門情報を参照しましょう。
常に慎重な姿勢を忘れずに
BIOSは直接的にハードウェアと接続するシステム部分です。一度の操作ミスが起動不良に直結する可能性があるため、「わからないものは触らない」が基本です。特に自己責任で行う自作PCでは、その意識がより必要になります。
BIOSは一度理解すれば大きな味方になりますが、その扱いには十分な注意が求められます。基本をしっかりと押さえ、安全かつ正しく操作することを心がけましょう。